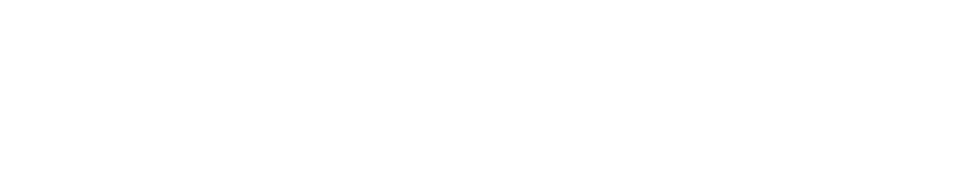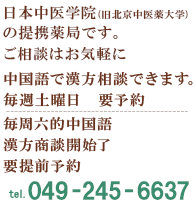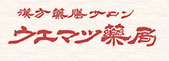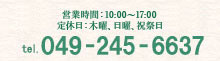-
二十四節気を用いた食提案 小寒
冬は来るべき春に備えてエネルギーを蓄える季節です。
中国の古典には
「夜は早く寝、朝は日が昇ってから起き、心の落ち着きを保ち、
衣類で保温を心がけて、腎の機能を滋養していく。
これが良い冬の養生方法である。」
と記載があります。
寒さや冷えは血管を収縮し血流を悪くさせるため、
神経痛、腰痛、生理痛などの痛みを引き起こすほか
高血圧や脳卒中、狭心症の原因にもなります。
マフラーや腹まきなど、体をいつも温かく保つ工夫を心がけましょう。
血流を良くする生姜やネギの入った温かいみそ汁など摂るのも良いですね。
また体の熱の多くは筋肉が生み出していると言われています。
室内でもできる体操や筋肉トレーニングを行って、
寒さに負けない体づくりに励んでみるのもおすすめです。
《旬の食材》
かぶ
秋冬のかぶは、甘味が増します。
葉にはカロテンやカルシウム、鉄分。
白い丸い部分にはビタミンCやカリウムが豊富です。
漬物や煮物、すりおろすなど、楽しみ方も豊富ですね。
消化不良、下痢、ゲップにおすすめです。
春菊
豊富なβ‐カロテンとビタミンCの相乗効果で肌荒れやシミを予防してくれます。
多くの香り成分が自律神経を整えてくれます。
イライラ・情緒不安・咳・目赤・めまいにおすすめです。
小寒(しょうかん)1月5日〜1月20日頃
一年で一番寒いこの時期を「寒」といい、小寒から始まるので、「寒の入り」といわれます。
一月七日には、一年を健康に過ごせるよう願って七草粥を頂きます。
春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(蕪)、スズシロ(大根)です。
写真:蝋梅・寒さに強く、花の少ない冬に咲く貴重な花です。
-
中医学は面白い。勉強してみませんか?
季節の生活養生や食養生は、中医学の養生法の本に書いてあることが、
今に伝わっているものが多くあります。
夏は早く寝て、早く起きる。冬は早く寝て、遅く起きる。
冷えが生理痛の原因だとか、
ストレスがたまると胸が張ってきて、しこりが出来、
乳がんの遠因になるとか、
なんと、2000年前の中国の養生書に載っています。
病気も季節と関係があるので、
季節と症状に合わせて漢方薬を選びます。
漢方と中医学は少し違います。
漢方は2000年前、寒い時代にできた傷寒論という本に載っている処方が中心です。
寒い時代ですので、風邪を治す処方が主ですが、中医学はその後さらに発展し、地球温暖化や
ストレス社会のアレルギーや、温熱病を治す現代病の処方がメインになっています。
その中医学を、きちんと系統的に学びたいと、
私は東京本郷にある、北京中医薬大学日本校に入学しました。
そして、人生が変わりました。
本場中国の、北京中医薬大学の元教授たちの授業を3年間受けて、中医学が良く理解できました。
中医学は、宇宙と人間の関係を見ながら、病気の予防と体質改善をする素晴らしい医学です。
一緒に勉強した仲間たちは老若男女色々ですが、どの人も
「人生でこんなに勉強が面白いと思ったことはない。」と目を輝かせておっしゃっています。
中医学コースは1年から3年コースがあり、毎月2回土日曜日です。薬膳コースは1年間です。
詳しくはこちら → 北京中医薬大学日本校