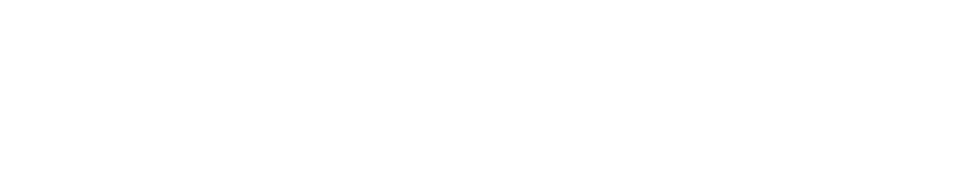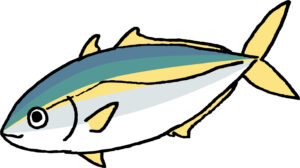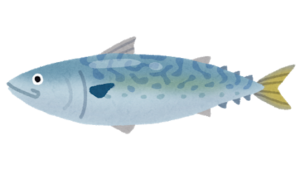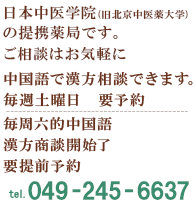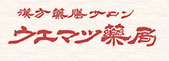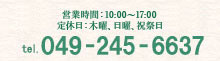-
二十四節気を用いた食提案 立春
立春(りっしゅん) 2月4日〜2月18日頃
春の兆しが現れてくる頃です。旧暦では、この季節から一年が始まりました。
立春を過ぎて最初に吹く南寄りの強い風を春一番と呼びます。
うぐいすは、春告鳥(はるつげどり)とも呼ばれ、春の兆しをつげるのです。
写真:梅とうぐいす
《食養生》
鍋物や炒め物に大活躍の野菜、ニラは、この季節に旬を迎えます。
そしてこの季節に特に効果的な食材です。
冬から春にかけて葉が厚く軟らかくなり、温性で辛味もあるため、体を温める作用が大きいのです。
冷えや血の巡りの悪い人に特に良いです。
そろそろ花粉が飛ぶ頃です。
早めの対策で症状を軽くすることも可能ですが、すべての病気の予防の基本は
バランスの良い、栄養素がしっかり摂れる食事です。
その食事の基本を頭に入れておくとよいです。
そのうえで、さらにその人の体質、症状にあったものを摂ればよいのです。
まず炭水化物・蛋白質・野菜を4:2:4の割合でとりましょう。
《旬の食材》
蕗の薹(ふきのとう)
雪解けの土の中から顔をのぞかせる蕗の薹は、春一番の山菜。独特の香りや苦味があります。
老化防止効果のある、ビタミンEが豊富。
咳、痰によく、血流促進の効果もあります。
さやえんどう
料理の彩りとしても活躍するさやえんどうは、さわやかな味わい。
ビタミンCやカロテンが多く含まれる緑黄色野菜です。
疲労・むくみにもよいです。
-
二十四節気を用いた食提案 大雪
冬は、活発な活動でエネルギーを消耗することは避け、ゆっくり過ごしましょう。
冷えから起こる風邪、関節痛や胃腸の不調に注意が必要です。
寒気を感じたら、温性、辛味のある食材で体を温めるのもいいですね。
大根、ねぎ、白菜が入った鍋はおすすめです。
冷えからくる胃腸の不調には、冷えを取り除き、温める効果のある、
シナモン、黒砂糖、八角、かぼちゃ、大豆、山芋、鶏肉のささみなどがお勧めです。
三首と言われる、首、手首、足首もしっかり冷え対策をして、冬を快適に過ごしましょう。
《旬の食材》
ぶり
寒ぶりといわれるように、寒い季節ほど脂が乗っておいしいぶり。体を温める食性があります。
高たんぱく、高脂質。血合いはタウリンが豊富。
元気を付け、補血作用があります。疲労、体力減退、知力低下、眼精疲労、貧血にもおすすめです。
ねぎ
体を温める食性があり、風邪予防、冷え性、鼻づまりによい。
ビタミンⅭ、βカロテン、カルシウム、葉酸ともに豊富。いずれも白い部分より葉に多い。
大雪(たいせつ) 12月7日〜12月21日頃
大雪(たいせつ)とは、いよいよ本格的に冬が到来するころのことです。
山々は雪に覆われ、平野にも雪が降り積もります。
写真:雪吊り
降雪地方では、雪の重みで木が折れないように、雪吊りをします。
大仕事ながら、冬の風物詩です。
-
二十四節気を用いた食提案 寒露
寒露(かんろ)10月8日〜23日頃
秋の夜長に、コオロギやキリギリスなどの虫の声が響きます。
コオロギの鳴き声の風情は早くも万葉集に歌われていたそうです。
(写真:ナナカマド:街路樹や庭木としても人気があり、秋には赤い実を沢山つけ、紅葉も美しいのが特徴)
《食養生の考え方》
食欲の秋、スポーツの秋などいろいろ言われますね。
姿勢を良くし少し早歩きをすると血流がよくなり、5分のウォーキングでも十分な運動になります。
体の筋肉を使い、内臓、関節を動かすと運動効果が高まります。
また、適度な運動はストレス発散にも効果的です。
食欲の秋ですが、食べる際は、まず良く噛むことを心がけましょう。消化吸収を良くしてくれます。
気持ちが沈みやすくなる秋です。
好きな匂いを嗅ぐ、読書、映画、音楽を聴くなど、リラックスして気の巡りが良くなるよう心がけて下さいね。
《旬の食材》
鯖(さば)
鯖の脂は血液をサラサラにしてくれます。青魚の大様と言われるほど、栄養豊富で、
疲労回復・老化予防・補血などの効果があります。
柿
柿に含まれる主な栄養素には、ビタミンC、β‐カロテン、カリウム、食物繊維があります。
柿は甘くて冷やす作用があり、二日酔・酒毒・口内炎・発熱時に良いです。
ただし冷やすので食べ過ぎにはご注意。
産後や冷え性、便秘の方も気を付けて下さいね。
-
二十四節気を用いた食提案 秋分
秋分(しゅうぶん)9月23日〜10月7日頃
日の出から日没までの昼と、日没から日の出までの夜の長さがほぼ同じになります。
中秋の名月や彼岸花や金木犀などもキレイな時期で、稲刈りが進み、風景もぐっと秋を感じるようになります。
(写真:金木犀)
《食養生の考え方》
秋は「肺」の乾燥にも注意:
秋になると空気が乾燥するので、皮膚、鼻、のど等も乾燥し、皮膚病や呼吸器の症状も悪化しやすくなります。
特にこの季節は肺をいたわるのが大事です。呼吸をゆっくり、深くし、意識して胸を張ったほうが、肺が広がり、健康になります。
粘膜や皮膚の粘膜が弱いと、気管支や鼻の不調につながります。
鼻洗浄もおすすめです。
お湯が体温と同じ温度、塩分濃度を1%にして、朝晩、鼻洗浄すると、すっきりします。
高齢の人はとくに体内の潤いが不足しがちになり、乾燥症状も出やすくなります。
日頃から健康を保つよう心がけましょう。
《おすすめ食材》
牛蒡
食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富。
便秘の解消、整腸、動脈硬化やガンの予防などに効果があります。
体内の余分な熱を取り除き、口の渇きや熱のある腫物、吹き出物を改善する効果もあります。

生姜
風邪の初期などに、しょうが湯を飲んで、寒さを追い出したり、
食欲増進、食中毒予防などが「生しょうが」の薬効としてあります。
「加熱したしょうが」は、体の中心からじんわり温めてくれるので、冷え性を根本から改善してくれます。
胃腸の血流も良くなるので慢性的な胃腸の弱りにもおすすめです。
-
二十四節気を用いた食提案 春分
進学、就職、人事異動など、環境の変化が多い時期です。
そんな中、ストレスが溜まると、イライラ・頭痛・肩こり・お腹が張る・
生理不順・不眠などの不調が出てきます。
カモミールやミントなど香りの良いお茶でリラックスしたり、
身体を動かしたりするなど、ストレスをこまめに発散するように心がけて下さいね。
食べ物は微量ミネラルを含むもの・牡蠣・抹茶・あおさ・納豆・卵・なつめなどがお勧めです。
微量ミネラルとは鉄・亜鉛・銅・カルシウムなど栄養素として欠かせない栄養素のことです。
《旬の食材》
アスパラガス
春から初夏が旬。カリウムやマグネシウムの吸収をよくし、
疲労回復を助けるアスパラギン酸を多く含みます。ルチン・葉酸も豊富。
口渇・むくみ・不眠・空咳にもよいです。
蕗(ふき)
食用とされる、一般的な品種は、主に愛知県で栽培されている「愛知早生」。
カリウム・カルシウムが含まれ、食物繊維はごぼう以上に多い。
解毒作用があり、また、咳を止め、痰の排出を促進する作用もあります。
《春分》
春分(しゅんぶん) 3月20日〜4月3日ごろ
春分は、太陽が赤道上にあり、地球のどこにいても昼と夜の長さが同じになる日です。
厳密にいうと実際には昼のほうが少し長いそう。
春分の前後3日を含めた7日間が春のお彼岸です。
先祖の霊を供養する仏事が行われますが、その他にも
日本では古来よりこの頃に農事始の神祭をしていたようです。