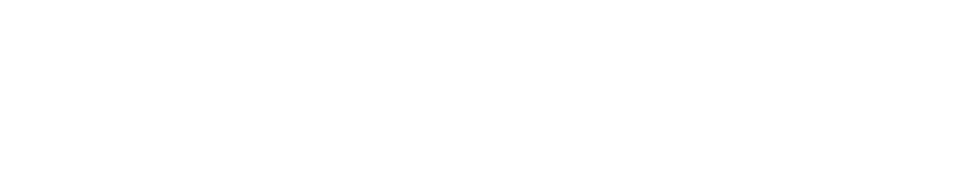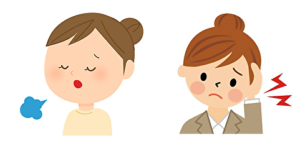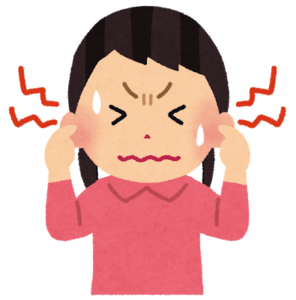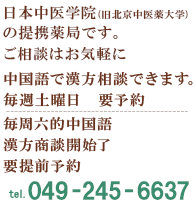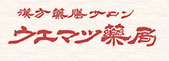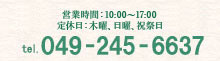-
耳鳴り・難聴対策5(胃腸虚弱タイプ)
《疲れやすい、胃腸虚弱タイプ》
*慢性胃腸疾患、貧血、病後などの人はこのタイプを参考に。
胃腸は飲食物から栄養を吸収し、「陽気(身体を温めるエネルギー)」や
「血」を生み出しています。
そのため、胃腸の働きが悪くなると、
耳にも十分な栄養やエネルギーが行き届かず、
不調が起こりやすくなるのです。
このタイプの特徴は、体内の「血」や「気」が不足しがちで、
疲れやすいこと。
耳鳴りや難聴の症状も重くなりやすいので注意が必要です。
まずは胃腸の元気を取り戻し、食事をしっかりとって
基本的な体力を養いましょう。
*主な症状
耳の症状:疲れると耳鳴りがする、聴こえにくくなる。めまい、立ちくらみ
その他の症状:疲労感、倦怠感、食欲不振、軟便、顔色につやがない
*食養生
~胃腸を整え、気血を養う
大豆製品(豆腐、納豆など)・そら豆・いんげん豆
米・鶏肉・ぶどう・黒豆・竜眼肉 など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
耳鳴り・難聴対策4(瘀血タイプ)
《慢性化に注意、瘀血(おけつ)タイプ》
*動脈硬化症、慢性頭痛などの人はこのタイプを参考に。
「血(けつ)」は全身を巡って栄養や潤いを届ける物質。
そのため、ドロドロ血や血管のつまりなどで
「瘀血(血行不良)」が発生すると、
耳にも十分な栄養が行き届かず、
耳鳴りなどの不調が起こりやすくなります。
このタイプは耳鳴りが慢性化して
聴力が落ちていることも多いので注意が必要。
瘀血の要因となる食生活の乱れ、身体の冷えなどを改善し、
血流をスムーズに保つよう心がけましょう。
*主な症状
耳の症状:慢性的な耳鳴り、聴力の低下、めまい
その他の症状:頭痛、胸痛、健忘、しびれ、顔色の黒ずみ、シミが多い
*食養生
~血管を健やかに保ち、サラサラ血流に
黒豆・なす・小豆・玉ねぎ・にんにく・紅花
わかめ・ひじき・サンザシ・酢・青魚 など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
耳鳴り・難聴対策3(痰湿タイプ)
《むくみやすい痰湿》
*肥満、高脂血症、メニエール症候群などの人はこのタイプを参考に。
身体の水分代謝が悪くなると、体内に「痰湿(余分な水分や汚れ)」が
溜まりがちになります。
すると、粘りのある痰湿(たんしつ)が耳にも停滞し、
閉塞感(詰まっている感じ)や耳鳴りなどの不調が起こりやすくなるのです。
このタイプは、まず身体に溜まった痰湿を取り除き、
水分代謝を良くすることが大切です。
そのためにも、暴飲暴食、脂っこい食事といった食生活を見直し、
胃腸の働きを良くするように心がけましょう。
*主な症状
耳の症状:耳鳴り、耳塞感(詰まっている感じ)、回転性のめまい
その他の症状:胃のムカつき、食欲不振、むくみやすい、太り気味
*食養生
~溜まった痰湿をすっきり取り除く
はと麦・どくだみ茶・冬瓜・きゅうり・れんこん
緑豆・春雨・ハスの葉茶・菖蒲茶・決明子 など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
耳鳴り・難聴対策2(肝うつタイプ)
《ストレス過多の肝うつ》
*更年期、高血圧などの人はこのタイプを参考に。
耳は清らかな「陽気(身体を温めるエネルギー)」の通り穴。
そのため陽気が十分にあり、スムーズに流れていれば、
耳は健やかな状態を保てます。
ところが、過度なストレスを受けると、体内の気の巡りが停滞し、
耳を流れる陽気もつまりがちになってしまいます。
その結果、耳鳴りなどの不調が起こりやすくなるのです。
このタイプの耳鳴りは突発的に起こる初期症状で、
キーンという高音が特徴です。
ストレスを発散させる「肝」を健やかに整え、
早めに対処し、慢性化を防ぎましょう。
*主な症状
耳の症状:キーンという高音の強い耳鳴り、ストレスを感じると重くなる
その他の症状:偏頭痛、不安、イライラ、怒りっぽい、口の渇き
*食養生
~ストレスを発散させて、気の巡りを良く
菊花・柿の葉・緑茶・マイカイカ茶・セロリ・ジャスミン茶・ミント など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
耳鳴り・難聴対策1
キーンという高音や、ジーと蝉の鳴くような音、
こうした実際にはない音を耳の中に感じる状態が耳鳴りです。
誰にでも起こる身近な症状です。
耳鳴りの主な原因は、耳の奥にある蝸牛の異常と考えられています。
ただ、そのメカニズムはまだ解明されていない部分も多く、
西洋医学では、薬で一時的に症状を抑えるなどの対処療法を取ることが一般的です。
一方、中医学では、耳の不調も身体全体のバランスが崩れたことで
起こると考えています。そのため、原因となっている身体の不調を改善し、
身体全体を耳鳴りの起こりにくい健やかな体質に整えることに重点を置いて対処します。
耳鳴りの主な要因となるのは、「陽気(身体を温めるエネルギー)」の不足や停滞などです。
他にも、胃腸虚弱や加齢なども耳鳴りが起こりやすい状態になります。
耳鳴りの多くは一時的なものですが、頻繁に起こると、精神的にも負担になります。
慢性化すると難聴にもつながりやすいので、注意が必要です。
耳鳴りを感じた時は身体のどこかに不調がおきているサインと考え、
早めの対処で症状を改善しましょう。
次回は、体質別の対策をお伝えします。
※耳鳴りは脳疾患や自律神経疾患などの病気が原因の場合もあります。
症状が長期化している人は早めに医師の診察を受けましょう。
ブログ一覧