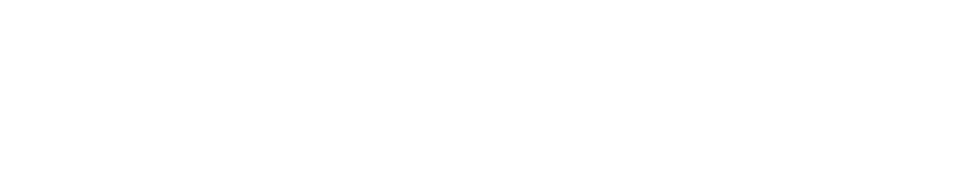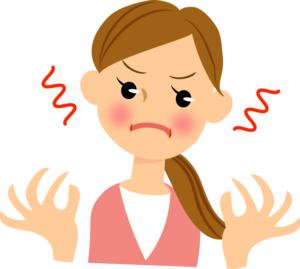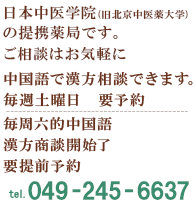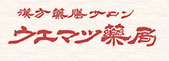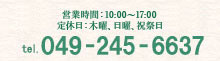-
PMS(月経前症候群)対策2・瘀血(おけつ)
血は「気(エネルギー)」と一緒に流れているため、
ストレスなどで気の巡りが停滞すると、瘀血(血行障害)を
招きやすくなることもあります。
また、体内の「血」は、「温かいとスムーズに流れ、冷えると停滞する」
という特徴があります。
ところが、月経前は女性ホルモンの影響などで身体が冷えやすい時期。
そのため、血も冷えて瘀血(血行障害)を招き、
痛みやしびれなどの不調が起こりやすくなるのです。
冷え症体質の人は、日頃から冷えをしっかり予防することが大事です。
温かい飲食、毎日の入浴などで身体を温めるよう心がけ、血行の良い状態を保ちましょう。
*気になる症状
・月経前の主な症状:痛みが強い(頭痛、胸痛、腹痛など)、肩こり
・その他:冷え症、手足のしびれ、月経痛が強い、
経血が黒っぽく塊が多い、舌の色が暗く瘀斑がある
*食養生
身体を温めて血流をスムーズに:
紅花、よもぎ、シナモン、黒糖、しょうが、玉ねぎ、長ねぎ、
小茴香(ういきょう)、サフラン など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
PMS(月経前症候群)対策1・気滞(きたい)
「肝(かん)」(肝臓)は、月経の基本となる「血(けつ)」を蓄え、
血量や月経周期の調節を担う臓器です。
また、ストレスを発散させて、「気」(エネルギー)の巡りを
スムーズに保つ働きもあります。
一方、ストレスが過剰になると、そのダメージで
肝の機能が低下してしまうこともあります。
すると、気の流れが停滞し、ストレスを上手く発散できず、
イライラや怒りといった精神的な不調が起こりやすくなるのです。
また、肝の不調は月経にも影響するため、
月経不順や月経痛などにつながることもあります。
「気滞」の状態は、PMSに多く見られます。
症状がそれほど重くないケースも多いので、
積極的なケアで改善を目指しましょう。
養生としては、日常のストレスをこまめに発散させることです。
肝を健やかに保ち、体内の気をスムーズに巡らせましょう。
*気になる症状
・月経前の主な症状:イライラ、怒りっぽい、乳房の張り・痛み、頭痛、肩こり
・その他:ストレスが多い、熱っぽい、口の渇き、過食、
月経時の下腹部の張り・痛み、舌辺が紅い、舌の苔が薄く黄色い
*食養生
香りの良い涼性の食材でストレスを発散:
ミント、ハマナスの花、ジャスミン、菊花、みかんの皮、
金針菜、黒きくらげ、うこん、春菊、三つ葉、竹の子 など
あなたに合ったお薬をお出しします。
今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
-
PMS(月経前症候群)は漢方で改善しましょう
多くの女性が感じる月経前の不快症状「PMS(月経前症候群)」は
適切なケアをすることで和らげることができます。
女性にとって月経は長い付き合いになるものだからこそ、
PMSの対処法をきちんと知って、
毎月の月経を上手に乗り切りたいですよね。
月経の1〜2週間くらい前になると現れる、
イライラ、落ち込み、不眠、胸の張り・痛み、下腹部痛、
頭痛、むくみといった不快な症状。
こうした心身のさまざまな不調を、総称して「PMS(月経前症候群)」
と呼びます。
排卵後の女性ホルモンの変化が関係していると考えられていて、
月経が始まると症状が軽くなることも特徴です。
PMSは、適切なケアをすれば不調を改善することも
できるので、諦めず積極的に対処しましょう。
中医学では、一人ひとりに現れる症状によって、
その根本原因を考え対処します。
原因がはっきりしないPMSは、一人ひとりの体質や症状に合わせて
柔軟に対応できる中医学の得意分野です。
体質に合わせた養生で不調を和らげ、月経と上手に付き合っていきましょう。
漢方を飲んで改善された方も大勢いらっしゃいます。
気になる方は相談にいらして下さいね。
※症状によっては、子宮内膜症などの病気が
隠れていることもあります。気になる場合は一度婦人科を受診しましょう。
-
咳、喉の痛みの対策・4 陰虚(いんきょ)
中医学では「のどは腎の潤いを受けている」と考えます。
これは、のどの状態と深く関わる肺が、腎と密接に関係しているため。
腎は体内の水分をコントロールする働きを担っていますが、
この機能が低下すると肺の潤いも不足し、のどの乾燥やかゆみが起こるのです。
肺・腎の潤い不足(陰虚)の人は、潤い不足で身体の熱を冷ますことができず、
熱がこもりやすいことも特徴です。
体内の潤いを十分に養いながら、余分な熱を冷ますよう心がけましょう。
*気になる症状
のどの症状:乾燥、弱い痛み・かゆみ、午後に痛みが強い、空咳、
痰が少ない、声が枯れる
身体のサイン:口の渇き、熱っぽい、舌の色が紅く苔が少ない
*食養生
身体の潤い養い、熱を冷ます:
干し柿、柿、梅、レモン、トマト、オリーブ、はちみつ、氷砂糖、ゆで卵 など
*健康的な暮らしのポイント
・毎日のうがいを習慣に。お茶や板藍茶(ばんらんちゃ)でのうがいも効果的です。
・たばこ、酒、辛いものは、のどを刺激するので控えめに。
・固い食べ物はのどを傷つけやすいので要注意。
・加湿器などで乾燥を予防しましょう。
・おしゃべりやカラオケは適度に。のどの負担を少なくしましょう。
参考:漢方の知恵袋
-
咳、喉の痛みの対策・3 肺気虚
「肺」はのどの状態と密接に関わっています。
そのため、肺の「気」(エネルギー)が不足していると、
普段から咳が出やすい、のどが痛いといった不調が起こりやすく、
免疫力が低下してかぜもひきやすくなってしまうのです。
この肺気虚(はいききょ)の方は消化器系が弱く、
栄養不足で気を生み出せないことも多いため、
まず胃腸を元気にして食事をしっかり摂ることが大切です。
体内の気を十分に養いながら、肺の働きを高めましょう。
*気になる症状
のどの症状:のどの不調を繰り返しやすい
身体のサイン: かぜを引きやすい、息切れ、疲労感、顔色が白い、舌の色が淡く苔が薄い
*食養生
気を養い、肺を健やかに:
大豆製品、山芋、米、しめじ、かぼちゃ、白きくらげ、百合根、白ごま、大根 など
あなたに合ったお薬をお出しします。
ご相談をお電話かメールでご予約下さい。
参考:漢方の知恵袋
ブログ一覧