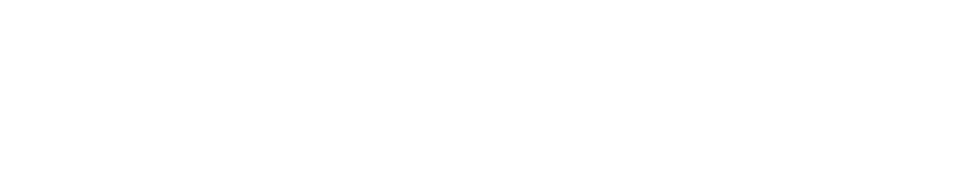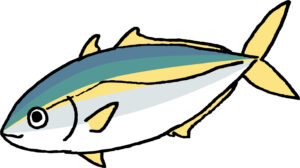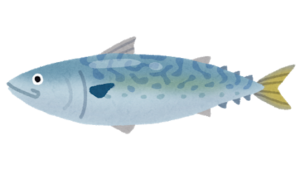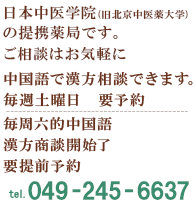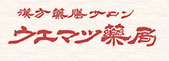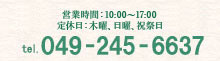-
二十四節気を用いた食提案 立春
立春(りっしゅん) 2月4日〜2月18日頃
春の兆しが現れてくる頃です。旧暦では、この季節から一年が始まりました。
立春を過ぎて最初に吹く南寄りの強い風を春一番と呼びます。
うぐいすは、春告鳥(はるつげどり)とも呼ばれ、春の兆しをつげるのです。
写真:梅とうぐいす
《食養生》
鍋物や炒め物に大活躍の野菜、ニラは、この季節に旬を迎えます。
そしてこの季節に特に効果的な食材です。
冬から春にかけて葉が厚く軟らかくなり、温性で辛味もあるため、体を温める作用が大きいのです。
冷えや血の巡りの悪い人に特に良いです。
そろそろ花粉が飛ぶ頃です。
早めの対策で症状を軽くすることも可能ですが、すべての病気の予防の基本は
バランスの良い、栄養素がしっかり摂れる食事です。
その食事の基本を頭に入れておくとよいです。
そのうえで、さらにその人の体質、症状にあったものを摂ればよいのです。
まず炭水化物・蛋白質・野菜を4:2:4の割合でとりましょう。
《旬の食材》
蕗の薹(ふきのとう)
雪解けの土の中から顔をのぞかせる蕗の薹は、春一番の山菜。独特の香りや苦味があります。
老化防止効果のある、ビタミンEが豊富。
咳、痰によく、血流促進の効果もあります。
さやえんどう
料理の彩りとしても活躍するさやえんどうは、さわやかな味わい。
ビタミンCやカロテンが多く含まれる緑黄色野菜です。
疲労・むくみにもよいです。
-
二十四節気を用いた食提案 小寒
冬は来るべき春に備えてエネルギーを蓄える季節です。
中国の古典には
「夜は早く寝、朝は日が昇ってから起き、心の落ち着きを保ち、
衣類で保温を心がけて、腎の機能を滋養していく。
これが良い冬の養生方法である。」
と記載があります。
寒さや冷えは血管を収縮し血流を悪くさせるため、
神経痛、腰痛、生理痛などの痛みを引き起こすほか
高血圧や脳卒中、狭心症の原因にもなります。
マフラーや腹まきなど、体をいつも温かく保つ工夫を心がけましょう。
血流を良くする生姜やネギの入った温かいみそ汁など摂るのも良いですね。
また体の熱の多くは筋肉が生み出していると言われています。
室内でもできる体操や筋肉トレーニングを行って、
寒さに負けない体づくりに励んでみるのもおすすめです。
《旬の食材》
かぶ
秋冬のかぶは、甘味が増します。
葉にはカロテンやカルシウム、鉄分。
白い丸い部分にはビタミンCやカリウムが豊富です。
漬物や煮物、すりおろすなど、楽しみ方も豊富ですね。
消化不良、下痢、ゲップにおすすめです。
春菊
豊富なβ‐カロテンとビタミンCの相乗効果で肌荒れやシミを予防してくれます。
多くの香り成分が自律神経を整えてくれます。
イライラ・情緒不安・咳・目赤・めまいにおすすめです。
小寒(しょうかん)1月5日〜1月20日頃
一年で一番寒いこの時期を「寒」といい、小寒から始まるので、「寒の入り」といわれます。
一月七日には、一年を健康に過ごせるよう願って七草粥を頂きます。
春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(蕪)、スズシロ(大根)です。
写真:蝋梅・寒さに強く、花の少ない冬に咲く貴重な花です。
-
二十四節気を用いた食提案 大雪
冬は、活発な活動でエネルギーを消耗することは避け、ゆっくり過ごしましょう。
冷えから起こる風邪、関節痛や胃腸の不調に注意が必要です。
寒気を感じたら、温性、辛味のある食材で体を温めるのもいいですね。
大根、ねぎ、白菜が入った鍋はおすすめです。
冷えからくる胃腸の不調には、冷えを取り除き、温める効果のある、
シナモン、黒砂糖、八角、かぼちゃ、大豆、山芋、鶏肉のささみなどがお勧めです。
三首と言われる、首、手首、足首もしっかり冷え対策をして、冬を快適に過ごしましょう。
《旬の食材》
ぶり
寒ぶりといわれるように、寒い季節ほど脂が乗っておいしいぶり。体を温める食性があります。
高たんぱく、高脂質。血合いはタウリンが豊富。
元気を付け、補血作用があります。疲労、体力減退、知力低下、眼精疲労、貧血にもおすすめです。
ねぎ
体を温める食性があり、風邪予防、冷え性、鼻づまりによい。
ビタミンⅭ、βカロテン、カルシウム、葉酸ともに豊富。いずれも白い部分より葉に多い。
大雪(たいせつ) 12月7日〜12月21日頃
大雪(たいせつ)とは、いよいよ本格的に冬が到来するころのことです。
山々は雪に覆われ、平野にも雪が降り積もります。
写真:雪吊り
降雪地方では、雪の重みで木が折れないように、雪吊りをします。
大仕事ながら、冬の風物詩です。
-
二十四節気を用いた食提案 立冬
冬は老化と関係した季節。まずはゆっくり休むことが老化防止につながります。
昼寝もおすすめです。10分程度寝るだけでも、午後の能率アップにつながります。
太陽の動きに合わせる様に、朝ゆっくり起きて夜は早寝するのもポイントです。
滋養強壮の食材を使った温かい料理を食べ、ゆっくり寝て体力を温存しましょう。
1日の寒暖差が大きい時期です。腹巻やネックウォーマーやレッグウォーマーなどで、
首回りや手首、足首をあたためるなど、冷え対策をして、冬を快適に過ごしましょう。
《おすすめの食材》
蓮根
肌の赤み・身体の熱感をとる。体を潤し、喉の渇きをとる。
胃腸を整えてくれる。食物繊維が豊富で腸を綺麗にする。
ビタミンC、ポリフェノールも豊富。
れんこんの穴は先が見通せて縁起がいい、と正月のおせち料理でも活躍します。
ほうれん草
緑黄色野菜の中で抜群に栄養が高いほうれん草。体内で
ビタミンAに変わるβカロテンは100gで約700μgあり、
1日の摂取基準を満たします。冬に収穫されたほうれん草は、
夏に収穫されたものに比べてビタミンCの含有量が3倍多いです。
不眠、精神不安、便秘、酒酔い、補血におすすめ。
立冬(りっとう) 11月8日〜11月21日頃
山にも里にも冬の気配が感じるようになる頃です。
風が冷たくなり、木々の葉が落ち、早い所では初雪の知らせが聞こえてきます。
11月15日は七五三の行事があり、数え年で男の子は3歳・5歳、女の子は3歳・7歳に成長を祝います。
さざんかや、スイセンの花が開き始める時期です。(写真:スイセン)
-
二十四節気を用いた食提案 寒露
寒露(かんろ)10月8日〜23日頃
秋の夜長に、コオロギやキリギリスなどの虫の声が響きます。
コオロギの鳴き声の風情は早くも万葉集に歌われていたそうです。
(写真:ナナカマド:街路樹や庭木としても人気があり、秋には赤い実を沢山つけ、紅葉も美しいのが特徴)
《食養生の考え方》
食欲の秋、スポーツの秋などいろいろ言われますね。
姿勢を良くし少し早歩きをすると血流がよくなり、5分のウォーキングでも十分な運動になります。
体の筋肉を使い、内臓、関節を動かすと運動効果が高まります。
また、適度な運動はストレス発散にも効果的です。
食欲の秋ですが、食べる際は、まず良く噛むことを心がけましょう。消化吸収を良くしてくれます。
気持ちが沈みやすくなる秋です。
好きな匂いを嗅ぐ、読書、映画、音楽を聴くなど、リラックスして気の巡りが良くなるよう心がけて下さいね。
《旬の食材》
鯖(さば)
鯖の脂は血液をサラサラにしてくれます。青魚の大様と言われるほど、栄養豊富で、
疲労回復・老化予防・補血などの効果があります。
柿
柿に含まれる主な栄養素には、ビタミンC、β‐カロテン、カリウム、食物繊維があります。
柿は甘くて冷やす作用があり、二日酔・酒毒・口内炎・発熱時に良いです。
ただし冷やすので食べ過ぎにはご注意。
産後や冷え性、便秘の方も気を付けて下さいね。
二十四節気を用いた食提案